
|
||||||
|
|
||||||
|
皆様いつもお読みいただきましてありがとうございます。 ワンスアラウンド顧問の馬場です。 今週は、『マーケットレポート』の第33弾をお届けします。 コロナ禍でのマーケットの変化と、商業施設を中心とする現場の変化をタイムリーに捉えながら、 自らも現場を持つ弊社ならではの視点で、これからの時代へのヒントをお届けしたいと思います。 |
||||||
|
【Market Report vol.33】 |
||||||
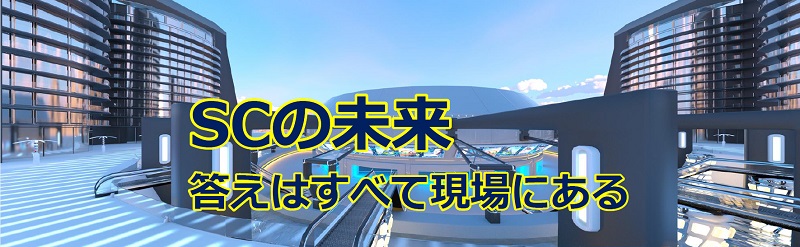
|
||||||
|
百貨店の再生・復活に向けて ~ショッピングセンター(SC)化の現在地~ |
||||||
|
百貨店は、地方店を中心に首都圏でも閉店が続いており、 山形・徳島などの「百貨店ゼロ県」も生まれているなか、 今後は、ターゲットを見極めたうえで、アパレルに拘らず、地域の人に寄り添い、 今までの様なフロア切りや用途切りのコンセプトではない 「新たな百貨店」の提案が求められると前回ご報告しました。 |
||||||
|
1970年代には既にあったSC化と専門店導入 |
||||||
|
近年は「消化仕入契約」から「定期借家契約」への切り替えによるSC化の転換事例が多くなっていますが、 SCへの転換や専門店導入は最近の取り組みではなく、1970年代にはすでに始まっていました。 前職の会社(以下:鈴屋)が出店した事例を報告します。 |
||||||
|
(1)百貨店からSC化された商業施設 ■千葉市 「奈良屋デパート」 →1972年、「千葉セントラルプラザ」に転換 →2001年 営業終了 ■鹿児島市 「大見高島屋」 →1979年、「高島屋プラザ」に転換、 のちに「タカプラ」に呼称変更 →2022年 地域一体開発で複合施設「センテラス天文館」として開業 ■川崎市 「岡田屋百貨店」 →1980年、「川崎岡田屋モアーズ」に転換 ■藤沢市 「十字屋」 →1986年、「藤沢コスタ」に転換 →1996年 「藤沢OPA」として全面改装 (2)東京発の専門店として百貨店に出店 鈴屋は上野で創業後、1960年代にファッションの発信地である銀座で「ファッション専門店」を確立し、 新宿、池袋、渋谷の各ターミナルに出店。 その後、1969年に初めて箱根を越えて、大阪梅田に出店しました。 当時、東京流の店舗や商品が通用するだろうか?との危惧がありましたが、 東京流を押し通した結果、東京と大阪という日本の2大経済圏の支持を受けたことが 全国展開の起点となり、1970年代に入ると全国主要都市への店舗展開が本格スタートしました。 そんな中、最初の百貨店からの出店依頼は、1973年(昭和48年)、 熊本市の「鶴屋百貨店」の増床改装時でした。 「鶴屋百貨店」は、婦人・紳士・靴・呉服等の各業種一店舗づつ、 東京の専門店の導入を計画し、「百貨店の顔として東京ファッションを発信して欲しい」との依頼で、 1階中央区画への出店でした。 その後1970年代後半には、地方都市の百貨店から、 「街の環境を明るくする」、「人の流れを惹き込む」と評価をいただき、 以下の百貨店では1階入口や中央区画に出店しました。 ■北海道 「丸井今井百貨店 (旭川店・函館店)」 「棒二森屋(函館)」 ■長野県 松本市 「井上百貨店」 ■三重県 四日市市 「近鉄百貨店」 ■山梨県 甲府市 「岡島百貨店」 |
||||||
|
百貨店・量販店のSC化で経験したこと。学んだこと。 |
||||||
|
SC化において、テナント側と企画・実施側、双方の立場を経験をしましたが、 SC化への業態転換の中では、2つの大きな課題(現在も同じですが)が浮き彫りになりました。 2つの事例をご紹介しますが、課題は大きく以下の2つではないでしょうか? (1)独自なテナント運営力(テナントとのコミュケーション力) (2)転換前とは違ったSC価値(利益構造)づくり |
||||||
|
||||||
|
現在も、多くのSC化への転換が計画されていますが、コロナ禍後に定着しつつある 「新しい生活様式」に対応する中、「新たなSCコンセプトで、 リアルな場としての体験価値や来館価値を向上させる」取り組みが求められています。 |
||||||
|
今秋、開業及び改装予定のSC化施設 |
||||||
|
そして今、SC化への取り組みでは、高島屋グループの計画に注目しています。
百貨店と専門店からなる「京都高島屋S.C.」の専門店ゾーンに、 今回、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下:CCC)、 高島屋、東神開発の3社による合弁会社 「TTC LIFESTYLE社」 による「京都蔦屋書店」が出店します。
「ライフスタイルや文化の発信・提案」が3社共通の強みですが、 今回の出店は、この3月27日、文化庁が移転した京都の地に、 「ライフスタイルコンテンツ」として、 「アートを中心としたライフスタイルを提案する店舗」となります。 今後の「新しいSCコンテンツ」としても注目されると思います。 |
||||||
|
変わる!!百貨店のSC化の推進役 |
||||||
|
百貨店は、自主編集の売場を手放しながら、テナントの導入にあたっていますが、 それをサポートしているのが、「東神開発」や 「パルコ」などのSC運営会社です。 SC運営会社は、テナント開発事業において大きな役割を果たしており、 ここに来て一段とクローズアップされています。 「東神開発」は、 二子玉川の「玉川高島屋S・C」をはじめ、 国内外の商業施設を開発、運営していますが、高島屋グループは、今後は 「東神開発」が「グループの軸」になると表明しています。 また、「パルコ」は、当初は西武グループとして 「池袋パルコ」を開業しましたが、 百貨店のグループ再編の中で、「J.フロントリテイリング」の グループ企業(子会社)としてSC事業を担い、 百貨店事業の「大丸松坂屋」を支えていましたが、 3月からは、「J.フロント都市開発(株)」に承継しています。 パルコの牧山前社長は、大丸松坂屋に無いもの、足りないものとして、 「アートやポップカルチャーを含めたエンターテインメント要素を取り入れ、 そのコアファン(若者)を獲得することが、大丸松坂屋の期待に応えることである」 と語っています。 両社は、奇しくも約半世紀前の1969年に、当時はまだ都心の郊外だった二子玉川に、 日本最初のショッピングセンターと言われる「玉川高島屋S・C」と、 池袋駅東口の丸物百貨店の跡地に「池袋パルコ」を開業させており、 「商業施設ディベロッパーの先駆者」としての不思議な縁を感じずにはいられません。 |
||||||
|
さいごに ―SC化が進む中での百貨店の役割と方向― 百貨店のSC化が進行する中、お客様から見ると、どんな契約形態で運営されているのかは特に問題ではなく、 百貨店とSCで異なるのは、地下の食料品、1階のコスメ、ラグジュアリーブランドくらいで、 殆ど変わらないと思います。 コロナ禍でEC売上が伸長している今、百貨店もSCも、 「リアルな現場としての価値を、より向上させる」ことが必要不可欠になりました。 具体的には、「魅力ある店舗づくり」「お客様を惹きつける(集まる)コンテンツ」 が求められており、その実現のためには、地域の人々に寄り添いながら、新たな視点が求められます。 前述した2社には、SCの新しいコンテンツとして「アートやポップなカルチャー」を志向している という共通点があります。 これは、百貨店のSC化の新たな方向性のヒントになるのではないでしょうか? |
||||||
|
||||||
このメールマガジンは、お客様によるご登録や名刺交換など、 弊社と何らかのご縁をいただいたお客様にお届けしております。 皆様からのご返信を筆者も楽しみにしております。ご感想などございましたら、 ぜひ本メールよりご返信下さい。 |
||||||
|
バックナンバーはこちらからお読みいただけます。 |
||||||

